学研『教育ジャーナル』は、全国の学校・先生方にお届けしている情報誌(無料)です。
Web版は、毎月2回本誌から記事をピックアップして公開しています。本誌には、更に多様な記事を掲載しています。
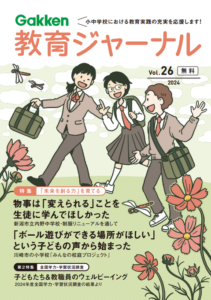
教育ジャーナル Vol.26-2
■「未来を創る力」を育てる①
物事は「変えられる」ことを生徒に学んでほしかった
新潟市立内野中学校・制服リニューアルを通して
全2回(第2回)
■「未来を創る力」を育てる①
物事は「変えられる」ことを生徒に学んでほしかった
新潟市立内野中学校・制服リニューアルを通して
【全2回】(第2回)
教育ジャーナリスト 渡辺 研
「千代田区立麹町中学校の改革」に刺激を受けたのか、数年来、中学校でこれまでの慣習を覆す取組が活発になってきた。
グループ学級担任制、部活動改革、校則や制服の見直し……。
そこに「生徒指導提要」(2020 年12 月)の「校則を制定してから一定の期間が経過し、その意義を適切に説明できない校則については、本当に必要なものか、絶えず見直しを行うことが求められる」(*)という後押し。
このような時代背景の中、新潟市立内野中学校では、生徒の声を反映しながら校則を見直し、制服の変更に取り組んだ。
生徒が参加して新しい制服を決める過程を通して、生徒たちが何を自覚したのか。生徒諸君の声を聞く。その第2回をお届けする。
*要約
◉ 残したいものは何?
改めて紹介する。夏休み前のある日の放課後、お話を聞かせてくれた生徒諸君は全員3年生。
女子生徒着用のネクタイやリボンは今年度から採用された新しいデザイン。参加してくれた一人は部活動の途中で参加してくれたので前出の体育着。一定の制限の中に自由がある。
なお、生徒諸君はたくさんのコメントをしてくれたのだが、こういうご時世なので、原則として、各コメントに名前の表記はしないことにした(前出のコメントも同様)。また、〝制服リニューアルプロジェクト〞はPT(プロジェクトチーム)と表記する。
2023年度早々に始まった制服リニューアルプロジェクトは、生徒会の2年生役員が主導して行うことになった。現役員の4人は当時からの役員。その後、PTが結成される。
「PTのボランティアを募る前に、全校生徒に『新しい制服をつくります。どんなのがいいですか』というアンケートを取りました。何もない状態から始めるので、どういうものにするかの指針になるように」「制服のテーマは『内野中らしさ』。内野中らしさを制服に出したいということで、『内野中といえばどんなものがあるのかな、どんなことが内野中らしいといえるのかな』ということを聞きました」
色や形のほかに、具体的にはこんな質問もした。
●今の制服から引き継ぎたいもの、残したいものはなんですか。
●新しく取り入れたいものはなんですか。
●どんな制服が理想ですか。
中学生はこんな穏やかな視点をもっている。決して〝破壊↓創造〞ではない。
色や形には「紫」「和装っぽいもの」「セーラー服」などという回答もあったそうだ。それらを含めて、意見や要望は何百種類にも上った。取組全体を通して、アンケートの集約が一番苦しかったという。
「多すぎて、しっちゃかめっちゃかで、こんなの全部は取り入れられないって。でも、一つずつ書き出して、似たものを分類して、タブレットにデータを全部打ち込んで……」
「〇〇ちゃんが、そういうのは得意!」
苦労の結果、「学校の75周年記念ゆるキャラ『ウッチュー』と、校区を流れる三川(3つの川の総称)をモチーフとして、考えていこうということになりました」。
具体的にはメーカーが2パターン、生徒たちが1パターンを提案する。ここからの作業は楽しくなっていった。
◉ 単に数で決めるのではなく
次のステップは生徒案の制服を考えるPTの結成。応募が殺到しそうだと思ったのだが、意外にそうでもなかった。
「最初、数人しか集まらなくて、『一緒にやりませんか』って勧誘もしました」
少しがっかりもしたが、「休み時間や放課後もつぶれるし、2、3回集まって終わるものではないので、なかなか踏みきれなかったのだろうと思いました」と理解した。
最終的には「私たちを入れて40人くらい集まりました」。1年生10人ほど、2年生は18人、3年生数人。
PTの仕事は、生徒会で考えたコンセプトをもとに、生徒提案の具体的なデザインを考えること。上着は紺色・無地のブレザー。柄もOKのスカートとスラックスを数十種類の生地を見ながら組み合わせを考える。ただ、ひと言で〝紺〞といっても色味は微妙に異なる。〝チェック〞といってもさらにさまざま。
40人はグループに分かれてそれぞれがトータル・コーディネートを考えた。基本的には楽しい作業だった。でも、ここでの苦労も十分に想像がつく。1グループ10人程度とはいえ、それこそ好みは十人十色。この難問に生徒たちはどう答えを出したのか。
「グループ内でも案がいくつか出て、メンバーで『これがいいよね』『あれもいいよね』と話し合っていたのですが、全然まとまらなくて。限られた時間の中で一つの案に絞るのが本当に難しかったですね」
多様な考えを出し合って協働して……言うのは簡単だが、現実にはかなりの難問。でも、とにかく答えを出さなければならない。
「とりあえず多数決を取って、多かった中で、『どうしてもこの服は嫌だっていう人はいない?』みたいな感じで一つに絞っていきました」
数で押し切るのではなく、最後まで少数意見も尊重する民主主義の基本姿勢を貫いた。
各グループから出された3つの案を一つに絞るのも、当然、大変だった。
「まず3パターンで多数決を取りました」
自分のグループ以外でどちらがいいかという形式で投票した。
「二つのデザインに人気があって、票がほぼ同じ。じゃあ、この二つで決戦投票しようってもう1回やったんですけど、やっぱり微妙な差で……」
ここでも、単に数では決めなかった。
「プレゼンもしました。『ここに力を入れた』『内野中らしさを出した』と言って、最後までみんなで悩んで、3回目の投票で、なんとか数票差で決まりました」
「どちらも採り入れたいくらい、いいものでした。みんなにもそういう思いがあったと思います」
それでも、ちゃんと納得解を見いだした。
「楽しかったです」と生徒会長は言った。
◉ ファッションショー
生徒たちは、決めたデザインをメーカーの担当者に伝えた。選んだ生地はグレーがベース。織柄のような感じでさりげなく赤や青のラインが入っている。
「内野中のシンボルカラーがえんじ色。内野は桜がきれいなので、それも組み入れて。そこに3つの川とゆるキャラ『ウッチュー』から連想した青が入っています」
〝自分たちが着る制服〞を考えるとこうなる。それは色や柄だけではない。
メーカーが提案した2パターン(A案・B案)は、スカートもスラックスも青を基調にしたチェック。そのチェックもスカートとスラックスでは少し違えてある。実際に着て動いてみるとプリーツの具合などにより見え方が違ってくるので、少し違うほうが逆に同じに見えるのかもしれない。プロの技。
「私たちが出したものは(C案)、生地も柄もまったく同じでした」
せっかく校則から男女の表記を削除したのだから……そんな意思表示に聞こえた。
メーカーにデザインを伝え、見本ができてきてからPTが企画したのがファッションショー。3つのパターンを全校生徒に披露する。1パターンにつき男子1人(スラックス+ネクタイ)、女子2人(スカート+リボン、スラックス+ネクタイ)。ただし、ショーの時点でのネクタイとリボンは仮デザイン。
ショーでは、モデル、司会進行、照明、撮影などをPTのメンバーが務めた。当日は地元テレビ局の取材も入り、朝、夕のニュース番組でも取りあげられた。
体育館に集まった全校生徒が見つめる中、3人1組で笑顔でランウェイを歩いた(2023年6月5日)。モデルが登場すると、そのたびにあがる歓声や拍手。PTのメンバーたちは、きっと誇らしかったことだろう。
「楽しかったです。でも、その前からずっと楽しかった。考えるのが楽しかったです」
◉ 新しい制服に切り替えたが……
3つの新制服モデルは校内に展示され、学校のHPにも載せられた。まず、A〜C案の上着とスカート・スラックスの組み合わせを決め、次にそれに合うリボンとネクタイ、ボタンとエンブレム、ブレザーの襟の縁どりを決めていく。リボン・ネクタイなどもPTで考えてメーカーに伝え、具体化してもらった。
決定は、いずれも全校生徒及び校区内の小学生、保護者ら約4800人の投票。その結果、新しい制服はメーカーから提案されたものに決まった。
「投票では選ばれず……」「悲しかったね」
インタビューの日、当時の資料を見ながら自然に話し込んでいた。
「グレー、よかったなあ」「制服は、やっぱり黒か青かってイメージなんだよね」「柔軟じゃない」「これだと入学式や卒業式で写真を撮るとき、顔が暗く写っちゃうんじゃないかなあと思ったんだけど」「赤はけっこう推したんですけど、スカート・スラックスに赤系統がなかったので、統一感がなくなって」
「ま、投票で決まったことなので」
ちょうど1年前の出来事なのに、今まだPTの作業中かのようでもあった。「なつかしい」とつぶやきも聞こえた。
こうして新しい制服が決まり、令和6年度から採用されたのだが、思ってもみない続きがあった。佐藤校長はこうおっしゃった。
「私は、リサイクルとか、『ムダにしない』をモットーにしているので、『一斉に全部を変えよう』とは言わない。新しい制服に切り替えましたが、今後も学生服もOKです。従来の女子のブレザーなどもOK。でも、制服デザインは全体のバランスを考えて決めたのだから、新タイプと旧タイプを上下で組み合わせる着こなしはしないようにと言いました」
2年生と3年生もフルセットの購入はできるが、それは経済的負担も大きい。でもせめて、せっかく頑張ったのだから旧タイプの制服に新しいリボンやネクタイの着用はOK。
校則から、性別表記と「可能」は削除されたものの、「学生服上下」はそのまま。だから今、制服だけでも新旧、スカート・ブレザー、リボン・ネクタイの組み合わせで9パターン。まだリボン着用の男子、学生服着用の女子は見かけないが、選択肢は増えた。
「その象徴がリーフレットの表紙です。『こうじゃなきゃいけないわけじゃないんだよ。みんながそれぞれ選択し、幸せになるような服装をしようよ』というのがコンセプトなのです」
古いものを何がなんでもなくしたのではない。制服という〝縛り〞は残った。でも、その縛りをずいぶん緩やかにしたことで、生徒たちは縛りに守られながら、今までよりも自由を感じることができている。こんな変革の仕方もある。
◉ ……なんとかなるんだな
C案は選ばれなかった。でもここは学校。〝競合他社〞に競り勝つことが目的ではない。生徒会とPTが活動した数か月の過程そのものに意味があったはずだ。
生徒諸君のインタビューの前に、佐藤校長はこうおっしゃっていた。
「一番のねらいは、生徒たちに『変えられるんだ』ということを、自信をもってやってほしかったんです。教師が主導するのではなく、生徒に委ねる。制服のデザインを変えることについて、いろんな意見を言える場を提供したかったのです。仲間と協働して、対話しながら最適解・納得解を出す」
それは間違いなく達成された。そして、中学生に願うことはもっと大きい。
「生徒たちは、われわれも経験をしたことのない時代を生きるわけですから、OECDが提唱しているエージェンシー(よりよい未来の創造に向けた変革を呼び起こす力)を育み、『新しい価値を創造する』『世の中を変えるために私たちは生きているんだ』ということを生徒に実感してほしかったのです。身近で『あれっ?』と思ったことや、『今の時代に合っていないな』と思ったことを、勇気をもってチャレンジして変えていく力が、皆さんにはあるのだよと、改めて言いたいです」
この経験を生徒たちはどう捉えたのか。
「生徒会に入って、このプロジェクトをやらせてもらったり、生徒会独自の取組があったりして、そういうところで自分たちからどんどん意見を出して、自分たちで考えて実践していくという場面が多いので、今回のことでもまた一つ成長して、今後、生徒会活動をするときに生かしていけるかなと、すごく思いました」
学びの過程や自身の変容を自覚できれば、また次の機会にも再現できる。
「このプロジェクトの前は、固定観念というか、『女子はこう、男子はこう』と捉えていた側だったんですよ。今回、みんなで考えを出し合って新しい制服を考え、日常的には聞けなかったけど、自分はこうしたいのだという考えが一人ひとりにあって、すばらしいと思いました。今まで、こういうふうに何かを成し遂げる経験がなかったのですが、中学生でも声をあげて、みんなで協力して考えていけば、無理かもしれないと思われることでも、なんとかなるのだと、そういうことを思いました」
自分たちで考えて行動する。夢中になって取り組む。それは楽しい。このような姿勢は今年度の体育祭にも表れて、今までにないストーリーのあるダンス応援などになった。
佐藤校長は、令和6年度入学式の式辞でこう述べていた(ホームページ「内野中だより」より)
〈(前略)これからの中学校生活をどのようにしたいと思いますか? 皆さんが、さらに学校へ通う理由は何でしょうか?
結論から言います。学校の成績はその後の人生ではたいした意味はありません。え、校長が「成績は意味がない」なんて言っていいのかな? と思うかもしれませんが、テストの結果、成績よりもさらに大切なことを、この内野中学校で身に付けて欲しいと願います。
それは、内野中学校の教育目標「自主」「他敬」「自愛」「創造」です。
これらは、テストの成績などの数字では測れない力です。ですから、自分はこの目標に近づけたのか、自分が、自分に厳しく振り返ることが必要です。(以下略)〉
今回のプロジェクトは、学校の成績でも数字でもない。でも、生徒諸君は、そこでの経験を学びとして実感し、自覚した。学校はそんな機会を設けてくれる場でもありたい。
【①了】
次回の予定
4月28日(月)
「未来を創る力」を育てる②

