学研『教育ジャーナル』は、全国の学校・先生方にお届けしている情報誌(無料)です。
Web版は、毎月2回本誌から記事をピックアップして公開しています。本誌には、更に多様な記事を掲載しています。
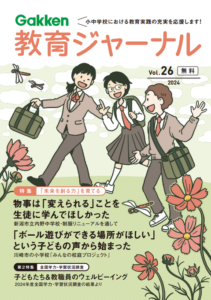
教育ジャーナル Vol.26-3
■「未来を創る力」を育てる②
「ボール遊びができる場所がほしい」
という子どもの声から始まった
川崎市の小学校「みんなの校庭プロジェクト」
【全2回】(第1回)
■「未来を創る力」を育てる②
「ボール遊びができる場所がほしい」
という子どもの声から始まった
川崎市の小学校「みんなの校庭プロジェクト」
【全2回】(第1回)
教育ジャーナリスト 渡辺 研
〝みんな=子どもたち・自分たち〟そう自覚して、本気になって取り組んだ子どもたち。
先生が見ていなくても、自分たちでルールを決めて、「みんなの校庭」をちゃんと管理できる。
◉ 放課後の校庭を児童に開放
「みんなの校庭プロジェクト」という取組が、今年度、川崎市の市立小学校(114校)で始まった。2023年度中に〝準備〞ができた95校でスタート、残り19校も工事で校庭が使えない1校を除いて24年度内に実施予定で、全校での展開になる。
名称からどんな内容と準備を想像されるだろうか。きっと、「みんな=子どもたち」なのだろうから、何かこう、子どもたちの主体性を促す取組……かもしれない。
始まりは子どもたちの声。その声を尊重した行政が、素早く後押しして実現した。
「みんなの校庭プロジェクト」は、放課後の校庭を子どもたちに開放するという取組だ。
「ほぉ!」と思われるかもしれないし、「なんで今さら?」と思われるかもしれない。今の時代、帰りの会が終わると、子どもたちは速やかに下校するものだと思っていたのだが、放課後の一定時間、校庭で遊んでから帰ることがOKの学校もあるようだ。
川崎市でも、もともと8割ほどの小学校では放課後の校庭が開放されていたそうだ。コロナ禍でも開放を継続していた学校もある。それは学校の管理下で実施され、当然、教師の見守りのもとで、子どもたちは開放された校庭で遊んでいた。いってみれば、「子どもたちのために」という教師の〝サービス〞によって成り立っていた。同様のことを今、教育委員会が奨励することなどできない。
では、従来の校庭開放と何が違うのか。それはどう実現したのか。
立ち上げからかかわっておられた、川崎市教育委員会事務局生涯学習部地域教育推進課の二瓶裕児課長にお話を伺った。
◉ 校庭=下校途中の広場・公園
川崎市では、全国に先駆けて、01年度から「子どもの権利に関する条例」が施行されている。その小学生版には次のように明確に書かれている。
◆子どもの意見も、おとなにはっきり伝えることができます。子どもの権利じょうれいでは、子ども会議というしくみがあり、子どもたちが自分たちの意見を市(市長)に伝えることができます。(第15条「参加する権利」、第30条「子ども会議」)
「みんなの校庭プロジェクト」も、この権利に基づいて始まった。ちなみに、子どもたちに同様の権利を保障した国の「こども基本法」の施行は23年4月。
そもそもは、こうだ。川崎市幸区で、市長が子どもの意見を聞く機会が設けられた(車座集会)。そのとき、区内の川崎市立古川小学校の児童たちから「自由にボール遊びができる場所がほしい」という声があがった。
全国各地には、それこそ昔の〝空地〞のようなダイナミックな公園を見かけることもあるが、住宅街の隙間にあるような公園(遊び場)では、往々にしてキャッチボールやサッカーなど、ボールの使用は禁止されている。乳幼児や高齢者も使う公園では、それも仕方がない。
前述のように川崎市の多くの小学校で放課後の校庭が子どもたちに開放されていた。だから「校庭で伸び伸び遊ぼう」というこのプロジェクト実現の下地はあったのだが、教師の働き方の現状を考えると、従来どおりの学校管理下での実施を、市が学校に求めるわけにはいかない。また、学校が管理するとどうしても「安全第一」にならざるを得ない。例えば「サッカーボールを使ってもいいけど、リフティングだけね」など、窮屈なルールが決められていたケースもあったそうだ。
「そこで私たちとしては、放課後の校庭を学校管理下ではなく『場の開放』と捉えて、子どもたちに、自由に遊んでもらおうと考えました」
〝学校の校庭〞ではなく、〝校庭=下校途中の公園・広場〞と捉えた。ただし、無条件に開放するのではない。
「使用にあたってのルールづくりを子ども中心にやろう。これを大前提にしました」
学校管理下から外すために、当事者である子どもたち自身が校庭の使い方や遊び方のルールを決める。肯定的な子ども観をもつ先生方の目はキラッと輝いたことだろう。
◉ 子どもたちによるルールづくり
きっかけとなった車座集会から何度かの集会を重ね(学校関係者や地域住民、古川小の児童や区内の川崎市立幸高校の生徒たちも参加)、21年12月の休日に「古川小学校大開放デー」を実施した(高校生も見守りのためにボランティア参加)。
これには「地域の校庭の存在意義や協働の取組による効果などについて、さまざまな立場、視点から検証」という確固たる目的があった(川崎市幸区ホームページより)。検討されているのは〝地域の校庭〞の活用だ。
実施後、さらに車座集会によって子どもたちの満足度が高いことを確認し、全校での実施に向けてスタートした。
まず全7区から各1校、モデル校を決めた。モデル校のミッションは、「(子どもたちによる自主管理を可能にする)子どもたちによるルールづくり」。「だったら任せてみよう」と、教師や保護者を納得させられなければ、このプロジェクトは実現しない。
二瓶課長は、あるモデル校の〝ルールづくりの話し合い〞に〝傍聴者〞として立ち会ったのだそうだ。
「いったん帰宅してから自転車で遊びに来たいとか、お菓子を食べたいとか、そういう話が出るのかと思っていました」
しかし、そんな話にはならなかった。
「例えば、『どうやればボール遊びとおにごっこは同時に遊べるのか、どう場所を分けようか』と、それを聞いたとき、びっくりしました。『どうやったら、みんなが安全に遊べるのか』ということを、子どもたちがストレートに発してくれました。ボール遊びは校舎側、おにごっこは反対側。下校はバラバラになるので帰りの門(出口)は1か所にしようとか、ランドセルはここに置こうとか、どうやったらみんなが安全に楽しく遊べるのかということを、子どもたちが真剣に考えてくれました。それを聞いて、『これを全校で進めていこう』という思いを強くしました」
枠組みとして、学校で決めるルールがあり、それはあとでふれるが、どこも開放時間は16時か16時半まで。教職員の勤務時間内なので校舎内には必ず教職員がおり、子どもだけでは手に負えない事態が発生した場合は、〝近くにいる一人の大人〞として、教職員が対応してくれる。でも、子どもたちはこんなことまで言ったのだそうだ。
「ある学校で『遊んでいて、ケガをしたときにはどうする?』と子どもに質問したら、『保健室の先生も忙しいから、救急セットを買ってくれたら、自分たちでやります』と答えたのですよ」
こんな健気な答えを聞けば、「大丈夫だ、進めていこう」と誰もが思うはずだ。ただ、安全のためにつけ加えておくが、川崎市では全校で学童(わくわくプラザ)がセットされており、学童のスタッフがケガなどのトラブルの初動対応を行うことになっている(あくまで緊急時の対応であって、常時見守りなど校庭開放の全責任をもつわけではない)。大人のほうでも、子どもたちの自主性、主体性を妨げない形で安全対策を整えている。
◉ 子どもたち自身が活動を管理
もう少し子どもたちの姿をお伝えしたい。
ルールの決め方は学級で話し合ってそれを集約するとか、学校それぞれだ。ある学校では、これまで校庭開放を行ってはおらず、校庭の開放は子どもたちにとって初めての体験。まず、5年生全員、約160名が体育館に集合してルールづくりの話し合い。グループ討議はなくいきなり全体交流だったにもかかわらず、活発な意見が出されたそうだ。子どもたちにとって、このテーマはまさに本気になって取り組める〝自分事〞。
「学年に関係なく遊ぶので、子どもたち同士の体格差を気にかける発言が出たりして、驚きましたね」
決めたルールも、自分たちでポスターをつくって他学年の子どもたちに周知を図った。
最初に取り組んだ古川小学校では、ルールを児童のタブレットにオンライン配信して徹底を図ったそうだ。
ノーチャイムの学校も多いが、それでも、校庭で遊ぶ子どもたちは、終了時間が近づく
と校舎の大時計で確認し、ボールなど使った道具を片づけ始める。
学校では〝備品〞を使えるようにしているが、当初は、ボールを紛失したりすると翌日の授業に支障が出るという心配があったため、教育委員会ではボールとかごを各校の子どもたちにプレゼントした。これは子どもたちが管理する。
こうしたモデル校の取組を経て、23年度から全校実施が始まった。
「これだけの数なので、いろいろな学校があるのは事実です。でも『遊び終わってボールが散らばっていることが多いからどうしようか?』と、自分たちで問題に気づいて、じゃあこうしようと考えて、やってくれているようです。『ボールがなくなったら遊べなくなる』と言って、自分が使ってなくても気づいた子が片づけるようになりました。立派です」(同課・大原幸浩課長補佐)
ルールをつくり、つくったルールを守れる。自分たちへの信頼がベースになって実現した〝自由にボール遊びができる広場〞だ。子どもたち自身がみすみすそれを手放すわけにはいかない。
【②-2に続く】
次回の予定
5月12日(月)
「未来を創る力」を育てる②-2

