学研『教育ジャーナル』は、全国の学校・先生方にお届けしている情報誌(無料)です。
Web版は、毎月2回本誌から記事をピックアップして公開しています。本誌には、更に多様な記事を掲載しています。
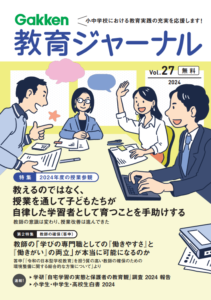
教育ジャーナル Vol.27-4
■2024年度の授業参観
中学校1年生英語科/小学校1年生体育科(スタカリ)/小学校6年生家庭科
教えるのではなく授業を通して子どもたちが
自律した学習者として育つことを手助けする
教師の意識は変わり、授業改善は進んできた
最後となる第4回は横浜市立本郷台小学校の家庭科の授業風景をご紹介する。
【全4回】(第4回)
■2024年度の授業参観
中学校1年生英語科/小学校1年生体育科(スタカリ)/小学校6年生家庭科
教えるのではなく授業を通して子どもたちが
自律した学習者として育つことを手助けする
教師の意識は変わり、授業改善は進んできた
全4回【第4回】
教育ジャーナリスト 渡辺 研
教科の特色のせいなのだろうか。あるいは、単元内での位置づけのせいだったのだろうか。
参観した授業では、教師は前面に出ることなく、子どもたちができるはずのことを引き出し、
夢中になれる手立てを工夫し、個や協働の場面を用意した。
そこで子どもたちは、声を出し、体を動かしながら楽しそうに学んでいた、
最後となる第4回は横浜市立本郷台小学校の家庭科の授業風景をご紹介する。
◆横浜市立本郷台小学校6年1組家庭科(専科・倉知優子教諭)
「『ゆでる』『いためる』の学習を生かしておいしいジャーマンポテトをつくろう」
◉ 学びを生活に生かしてこそ
授業の目当ては「今までに学習したことを生かして調理実習を成功させ、これからの生活に生かそう」。
そして、①手順を考えて、効率よく作業をすすめよう、②グループで協力し、すすんで行動しよう、③今までに学んだことを生かして安全に調理しよう、④「ゆでる」「いためる」のよさを感じながらジャーマンポテトのおいしさを味わい、これからの生活に生かそう。
学校での教育活動では①〜③が大事。学校はこういうことを学ぶ場だ。でも、家庭科という実用性の高い教科の特性を考えると、子どもたちに本当に身につけてほしい態度や力は④。家庭科は、低学年の生活科よりももっと、現実の人間の生活に密着している。
そういえば、洗剤を含んだ生活排水やごみの分別・減量など環境問題をいち早く取りあげ、子どもたちのエコ意識を育てたのは家庭科だったと思う。
6年生なので、すでに調理は何度か経験しており、包丁、鍋やフライパンはひととおり使える。「(じゃがいもを)ゆでる」も「(葉物野菜を)いためる」も経験ずみ。だから、たぶん③は大丈夫のはず。
ただし、両方が同時に必要なメニューには初チャレンジ。既習事項の応用編になるので、①や②をよく考えなければならない。特に①は生活に生かすときの大事なポイントだ。
家庭科の授業を参観するのは久しぶりになるのだが、この授業は、記憶にある授業とはちょっと違っていた。場面の所々に倉知先生のコメントを挟みながら、授業の様子、調理の進行を紹介していく。
◉ 自分の分を自分でつくる
4人で一つの調理台を使用。ガスコンロは2口。鍋、フライパン、まな板、ピーラー、包丁等は2セット。〝われ先に〞ではなく協力し合って使用する。材料はじゃがいも、玉ねぎ、ベーコン。塩と胡椒で味つけする。
メインの食材を子どもたちは〝個々に〞用意していた(じゃがいも1個、皮をむいた玉ねぎ4分の1個、ベーコン)。1グループに4人分が用意してあって、手分けして調理を進めていくのかと思っていたのだが、そうではなかった。もちろん、理由があった。
「以前はグループでつくることが多かったのですが、コロナ禍で調理実習ができなくなりました。再開したとき、どうしようかと考えて、〝自分の分は自分でつくろう〞ということで再スタートしました」
言われてみればそのとおりで、現実の生活では下ごしらえから完成まで、誰かが通して料理をつくる。グループで調理すると〝じゃがいもの皮をむく係〞〝玉ねぎを切る係〞など手分けした作業になりそうで、それではジャーマンポテトづくりの全工程を体験することができない。味つけだって、何をどのくらい入れればこんな味になるのかと実感しておかないと、実生活では生かせない。
「時間内に全員が出来上がるのか、不安はありました。でも、やってみたら、〝自分の分を自分でつくって食べる〞ことに、子どもたちが〝やらなくちゃいけない〞〝人任せにできない〞という気持ちになり、〝自分でつくったものはおいしい〞と感じていました。それで、メニューによって、一人ひとりで調理をするようにしています」
さて、自信をもって家庭の食卓に出せるジャーマンポテトができたのか。
◉ やってみると、やっぱり難しい
じゃがいもをタワシで洗うところから調理は始まった。あとで皮をむくのだが、子どもたちは入念にタワシでこすり続ける。続いてピーラーを使って皮をむき、芽を取る。手つきはちょっと危なっかしくても、態度は真剣そのもの。
授業には学校栄養職員も入っていた。調理台の間を歩いて子どもたちの様子を見守り、助けを求められたときにはサポートする。
「5年生のときに、じゃがいもをゆでる学習はしています。芽の取り方は経験があるのですが、そのときはゆでてから皮をむいたので、ピーラーは使っていないんです。事前学習で『お家でピーラーを使ったことある? できる?』と聞くと、『できる、できる』と言うんです。使い方はわかるので、頭ではできているんですけど、実際にやってみると難しい」
皮をむいたじゃがいもは厚さ5ミリに切ってゆでる(5分程度)。玉ねぎは薄切り、ベーコンは1センチ幅。
「玉ねぎの薄切りは難しいので、事前に『こうやって切るといいよ』と説明すると、ウン、ウンと聞いてるんですけど、その場になるとやっぱり『先生、どうしよう』と声がかかります。頭ではわかっているつもりでも、やってみて初めて『あ、こういうことだったのか』とわかります」
竹串を刺してじゃがいものゆで加減を確認し、ザルにあけて水を切り、薄切りにした玉ねぎとベーコンと合わせて炒める。ここでも慎重で丁寧。目安は示されていても、初心者はたいてい長めになりがち。
「〝強火でおよそ何分〞という目安はあっても、それに頼るのではなく『自分で様子を見ながら考えてやってみてね』と言っているのですが、それも意外に難しい」
食べながら、「あはは、塩かけたらポテチになった」と愉快そうに笑っている子もいた。ここはまだ、失敗が可能な場。次はジャーマンポテトをつくろう。
混雑した〝調理場〞で、「フライパン、通ります」と子どもの声が聞こえる。菜箸を操る手つきはまだおぼつかなくても、安全に調理をする態度は身につけたようだ。
◉ 実用的な生きる力を育む
出来上がったら、ほかの子を待つのではなくすぐに食べる。早い子は早い。最初に完成させた女子児童に「家でもやっているの?」と声をかけると、「ウン」とうなずく。「ベーコンだから、あんまり塩は入れなくていいんだよね」と言うと、「ウン」とうなずく。短い返答だが、経験は明確にものをいう。
「私は『お家チャレンジ』という提出箱を開放しているんです、『お家でもつくったら送ってね』と言って。けっこう送ってくれるので、すごくうれしいです。授業でやってみて楽しかったから家でもつくってみようと思い、そこでご家庭が協力してくれて、家族の食事のメニューをつくるというのは、素敵です。それが生きる力にもつながっていくと思います」
調理にかぎらず、衣服のこと、居住空間のこと、環境のこと、お金のことと、本当に家庭科は実用的な生きる力を子どもたちに育む教科だ。
各家庭はさまざまな事情を抱えている。夕方、お腹を空かせて保護者の帰りをただジッと待つのではなく、冷蔵庫にある何か食材を使って簡単な料理をつくれる力も必要だ。〝自分の分を自分でつくる〞。何気ないやり方にみえるが、実は大事な学びであり経験だ。
【了】
次回の予定
7月22日(火)
部活動のあとに何が生まれてくるか

