学研『教育ジャーナル』は、全国の学校・先生方にお届けしている情報誌(無料)です。
Web版は、毎月2回本誌から記事をピックアップして公開しています。本誌には、更に多様な記事を掲載しています。
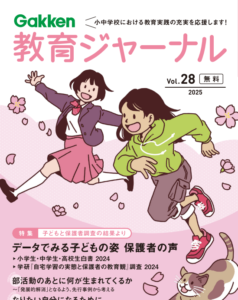
教育ジャーナル Vol.28-1
■部活動のあとに何が生まれてくるか
部活動改革が「発展的解消」となるよう、先行事例から考える
部活動の地域展開が徐々に進行している。
中学校の放課後に、生徒の新たな活動の場をどのように創造するか。
【全3回】(第1回)
■部活動のあとに何が生まれてくるか
部活動改革が「発展的解消」となるよう、先行事例から考える
部活動の地域展開が徐々に進行している。
中学校の放課後に、生徒の新たな活動の場をどのように創造するか。
全3回【第1回】
教育ジャーナリスト 渡辺 研
◆ 地域移行から地域展開へ
部活動改革の第一段階「公立中学校の休日の部活動を地域に移行」の期限(2025年度末)が近づき、急にかけ足になってきた。昨年12月、中学校学習指導要領解説には次の“なお書き”が加えられた。
〈なお、部活動は教育課程外の活動であり、その設置・運営は法令上の義務として実施されるものではないことから学校の判断により実施しないこともあり、また、全ての生徒が一律に加入しなければならないものではなく、生徒の自主的・自発的な参加により行われるものであることにも留意すること。〉
また、スポーツ庁・文化庁は、部活動の地域移行に向けた取組を検討する「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」中間とりまとめを発表した。
注目は「『地域移行』という名称を『地域展開』に変更」だ。
今ある部活動の形のまま運営を地域に移すのではなく、「学校内で運営されてきた活動を地域に開き、地域全体で支えていく」という改革のコンセプトは、地域展開という言葉のほうがしっくりくる。少子化・小規模化、校内の指導者不足、働き方の改善など、学校が抱える事情の解決策としてだけではなく、社会全体で子どもたちを育てようということを、少なくとも21世紀になって以来、ずっと目指してきていた。
ただ、曖昧さも残る。23~25年度の「改革推進期間」後の、26~31年度の6年間を「改革実行期間」として、「休日については、この期間内に、原則、全ての学校部活動において地域展開の実現を目指す」とされている。一方、平日については「各種課題を解決しつつ更なる改革を推進」とだけ書かれた。
神戸市では、26年度夏をめどに従来の学校ごとの部活動は廃止して、市内の中学校の部活動を「KOBE◆KATSU(コベカツ)」という新しい形態で地域展開する(詳細は市のHP参照)。学校間の連携も必要となるため、自治体が基本方針を示すことは大事だ。
中間とりまとめは、そこまで踏み込んでいない。逆に読めば、「31年度までに休日のみ地域展開を実現すればよい」ことになる。次期学習指導要領の実施もそのころなので、「学校判断で実施してもいい」状態も、少なくともそれまでは続く。地域展開の実現には、「中学校(の教育活動)には部活動が不可欠だ」と考える人たちの“納得”も必要だ。
こうした動きに先行して、新潟市立白新中学校(金山光宏校長)は23年度から学校での部活動を廃止、独自の活動を開始した(本誌Vol.19)。この「ブカツイノベーション」は23年度NITS大賞を受賞している(取組はNITSのHPプレゼン動画参照)。
白新中の取組に関心をもたれた高田彬成先生(帝京大学教育学部教授、元文部科学省及びスポーツ庁教科調査官)の学校視察にご一緒させていただき、白新中3名の先生方とのやりとりを含め、取組の現状、成果や課題を紹介させていただく。
廃止したあとに何を生み出せるか。“納得”の参考にしてほしい。
◆ いったんゼロにしてから発想
白新中の部活動改革の概略はこうだ。
基本方針は、①平日の活動も含めて検討する ②現状の部活動を移行するという考え方はしない ③地域の協力を得て学校と地域で役割を分担する
すでに地域展開が意識されていた。
「教職員には、部活動にかかわりたいという思いがあるので、『休日だけ地域に』といっても、『じゃあ、土日はお任せします』と割りきることは難しい。また、その形をうまくマネジメントできないとダブルスタンダードになってしまう。そういうことを考えて平日を含めて改革しました」(構想・制度設計の段階から改革を推進してこられた堀里也教諭)
この方針のもと、まずは部活動が当たり前だった放課後をいったんゼロにした上で(学校では部活動を行わない)、空いた時間と場所をどう使うかと考えた。中途半端に一部を残すよりも発想が自由になる。
そうやって考えられたのが、放課後の時間を生徒がデザインする「放課後デザイナー活動(以下、放課後D)」だ。イメージとしては同好会。生徒自身が“思い切りやりたい活動”を企画(選択)して、体育館や特別教室などを使って実行する。放課後の時間や施設の活用を生徒の意向に任せる形にした。
教師は放課後Dごとに“担当”になるが、部活動顧問的な指導をするわけではなく、活動にずっと付き添うわけでもない。これが週2日、16~17時。学期ごとに活動を募集、継続も可。学校単位の大会等には参加しないが、12月には校内で生徒主催の発表会もある。
一方、部活動を本気でやりたい生徒たちをどうしたのか。学校運営協議会(CS)がクラブを募り、審査を経て委託したクラブ(青少年の健全育成を目的とした団体、持続可能性等)が学校施設を使って活動を行う。これが「部活動」に代わる「白新ユナイテッド(以下、白新U)」(平日17~19時。週末等休日のうち1日。長期休業中も同様の時間設定。曜日はクラブ間でシェア)。希望する生徒はここで活動する(各クラブが設定する月謝がかかる)。他校の生徒も参加しており、公式の大会にも参加できる。移行ではなく地域展開の一つの形といえる。
付け加えれば、白新Uの活動があるため、学校では17時以降は生徒がかかわる活動は行わない。おかげで教師は放課後に“自分の時間”ができ、心身にゆとりが生まれた。
「当然だと思ってやっていた大会の引率や部活動の運営の仕事がなくなってみて、それが授業の準備や研修の時間をずいぶん削っていたことに、部活動をなくしてみて改めて気づかされました」(堀教諭)
教師にとっての改革にもなった。
【第2回に続く】
次回の予定
8月4日(月)
部活動のあとに何が生まれてくるか②

