学研『教育ジャーナル』は、全国の学校・先生方にお届けしている情報誌(無料)です。
Web版は、毎月2回本誌から記事をピックアップして公開しています。本誌には、更に多様な記事を掲載しています。
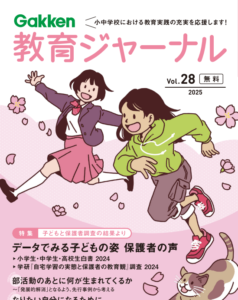
教育ジャーナル Vol.28-2
■部活動のあとに何が生まれてくるか
部活動改革が「発展的解消」となるよう、先行事例から考える
部活動の地域展開が徐々に進行している。
中学校の放課後に、生徒の新たな活動の場をどのように創造するか。
第2回は、改革からほぼ2年を経て見えてきた課題や新たな活動の芽吹きをご紹介する。
【全3回】(第2回)
■部活動のあとに何が生まれてくるか
部活動改革が「発展的解消」となるよう、先行事例から考える
部活動の地域展開が徐々に進行している。
中学校の放課後に、生徒の新たな活動の場をどのように創造するか。
第2回は、改革からほぼ2年を経て見えてきた課題や新たな活動の芽吹きをご紹介する。
全3回【第2回】
教育ジャーナリスト 渡辺 研
◆ 「先生方はこんなに大変な仕事を」
改革からほぼ2年。まず、堀教諭に挙げていただいた課題や成果を整理する。スポーツ庁や神戸市の方針を具体的に進めていけば、同様のケースも生じてくるはずだ。
【白新U】(地域で保障する環境)
・生徒は、放課後すぐに活動したいという(調整は難しい)。
・午前中で授業が終わった日や長期休業中は、早い時間から始めたい(検討中)。
・指導者を育成するシステムが働かないとハラスメントのリスクが高まる。
・CS内に設立されているが、事務局は教員が担当。連絡・調整役を誰が担うかが課題。
・音楽クラブは23年度に保護者が設立・運営し、音楽教諭が兼職兼業で指導。地域の音楽イベントや
吹奏楽連盟のアンサンブルコンテストなどに出場した。しかし、次年度は加入生徒が少なく、
保護者による運営も大変で活動の維持が困難になり、1年で休止。
「代表の方(保護者)が私たちに『先生方は部活動のためにこんな大変なお仕事をされていたんですね』と言ってくださって、それをわかっていただけただけでも、改革を進めてよかったと思いました」(堀教諭)
【放課後D】(学校で保障する環境)
・ポートボールとバスケットボールを組み合わせた〝ニュースポーツ〟を生徒が考案(体育授業から
発想)、大会も企画した。でも、ブレイキンなど本格的なニュースポーツはまだ登場していない。
eスポーツもまだ。生徒の側に「そんなこともやってもいいの?」という遠慮もあるらしい。
・運動部活動が担えなかったレク的な活動が誕生(ドッジボール、おにごっこ等)。
・生徒の主体性を尊重するが、教師による安全管理・安全指導が必要な場面がある。
・教員の異動があるため、部活動との違いについて年度当初に理念の共有が必要。
・部活動の加入率は約8割だったが、放課後D参加率は半分以下。無関心層が多く、
この掘り起しが課題。
・3年生の〝息抜き的な参加〟も期待していたが、3年生の参加率は低い。
・参加している生徒には「楽しい」「放課後の居場所」という役割は果たしている。
・部活動と違って縦のつながりが弱い(なくなった)。生徒たちもそれを認識しており、
改善策のひとつが、生徒の発案による発表会等のイベント。
◆ たとえ部活動がなくなっても
まだまだ課題はあるが、一方で“更地(ゼロ)”からは新しい芽吹きがあった。24年度、放課後Dから二つの活動が生まれた。
一つ目。女子生徒が、和太鼓をやりたくて「万代太鼓デザイナー」を立ちあげ、活動を始めた。ここに地域から、「地域の新潟まつりで太鼓をたたいて、中学生の手で祭りを盛り上げてもらえないだろうか」というオファーがあり、実現した(活動は継続中)。
二つ目。新潟市にも能登半島地震の被害があり、5月の防災学習をきっかけに、生徒から「みんなが楽しく学べる防災イベントをやりたい」という声があがった。地域と協力し、小学校にも呼びかけ、ともすれば高齢者の参加に偏りがちな地域の防災訓練を、防災イベントとして中学生の視点で地域住民に広げることに努めた。10月に「防災ワクワク大作戦」を実施、28名の生徒が運営にあたった(教師は有志が参加)。
「放課後Dが地域と重なってほしいという私たちの願いがあったのですが(放課後Dの地域展開)、それが実現したのが、2年目の進化です」(堀教諭)
地域展開は、学校が部活動を通して行ってきた生徒たちの育成を、代わりに地域が担うだけではなく、双方向のかかわり合いを目指す。“ポスト部活動”の一つの形だ。
「中学生になったら、“学校にある部活動”に入る」という選択肢がなくなったことで、中学生たちは、自分は何をやりたいのか、この場でこの時間で自分たちは何ができるのかを探し始めた。学校は、児童・生徒にそういう機会を設ける場でもある。
芽吹きをもう一例、あとで紹介する。
◆ フレックスタイムという選択肢
説明を受けたあと、16時からの放課後Dと17時からの白新Uを見学したのだが、その前に、高田教授からこんなお話があった。内容は、白新中の取組とは相反するものだったの
だが、あえて紹介する。
学校を取り巻く状況が変化して従来のような実施形態が持続不可能になっただけで、部活動そのものが否定されたわけではない。だから「地域移行」に納得し切れない生徒や教師、保護者がいる。高田教授は「ここでする話ではないかもしれませんが」と断って、その気持ちをくんだ話をされた。
「先生方の中には、顧問をやりたくはないけれどやらざるをえない方と、むしろ積極的にやりたい方とがおられると思います。それを一律に『先生方は部活動から手を引け』と言うのは、いい方法ではないと思っています。私の勤務校でも、中学校の保健体育教師志望の学生は、たいてい部活動の顧問をやりたいと言います。中学生にとっても部活動は学校生活の一部で、そこで先生が指導することのよさは間違いなくあります。先生方の実情に応じたやり方ができれば、まだ学校が子どもたちを引き取れるのではないでしょうか」
そうおっしゃって、ある提案をされた。このやりとりの中で別の選択肢も出たのだが、それは白新U見学のあとでふれる。
「先生方の勤務体系にフレックス制を導入してはどうかと思っているのです。部活動をもつ先生は、例えば3校時から出勤し、部活動終了の19時くらいまでの勤務にする。研究室でシミュレーションしてみたのですが、やりようによっては可能です。もちろん、部活動の顧問に限らず、子育てや介護などの事情がある先生にも適用できます」
24年8月の中教審答申でも「早出遅出出勤やフレックスタイム制度は、(略)教師一人一人のワーク・ライフ・バランスの実現に資するものである」と提言された。
もしも、部活動の課題が教員の勤務実態だけという学校なら、フレックス制導入によって働き方の改善と部活動の両立も期待できる。学校教育における「当たり前の見直し」が進行しており、“あと戻り”ではなく“選択肢”として検討されてもいいのではないか。
堀教諭を引き継いで取組の推進を担当する田淵将天教諭は、こうおっしゃる。
「ぼくは、典型的な“部活動を取りあげてほしくなかった教員”の部類に入ります。教師って、自分の時間を割いてでも『子どものために』とか『一緒に夢をもって』とか、そういう感覚が強かった。でも、それが当たり前であってはいけない、そこに問題があると、白新中にきて『なるほど』と思い、学んでいます。それでも、部活動を通して子どもとかかわることへの思いはあるので、フレックスはいいと思います」
まだまだ多くの中学校教師がもっている“思い”を無視しては、納得は得られない。では、すでに部活動がない中学校の様子を、生徒の姿を通して見ていきたい。
【第3回に続く】
次回の予定
8月18日(月)
部活動のあとに何が生まれてくるか③

