学研『教育ジャーナル』は、全国の学校・先生方にお届けしている情報誌(無料)です。
Web版は、毎月2回本誌から記事をピックアップして公開しています。本誌には、更に多様な記事を掲載しています。
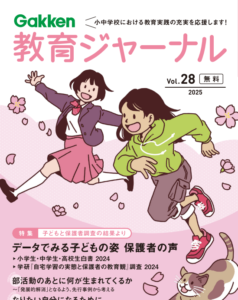
教育ジャーナル Vol.28-3
■部活動のあとに何が生まれてくるか
部活動改革が「発展的解消」となるよう、先行事例から考える
部活動の地域展開が徐々に進行している。
中学校の放課後に、生徒の新たな活動の場をどのように創造するか。
最終回では、生徒の実態を紹介するとともに、改革の意義や今後の展望について考える。
【全3回】(第3回)
■部活動のあとに何が生まれてくるか
部活動改革が「発展的解消」となるよう、先行事例から考える
部活動の地域展開が徐々に進行している。
中学校の放課後に、生徒の新たな活動の場をどのように創造するか。
最終回では、生徒の実態を紹介するとともに、改革の意義や今後の展望について考える。
全3回【第3回】
教育ジャーナリスト 渡辺 研
◆ 自分たちが学校をつくっていく
放課後Dの見学に体育館に行くと、キャッキャとはしゃぐ声、バタバタという足音。そこで繰り広げられていたのは「おにごっこ」。女子も男子も一緒になって、体育着や中には制服のまま、フロア中を本気で駆け回る。あまりの屈託のなさにつられて楽しくなり、思わず笑ってしまった。1年生の集団だ。
好き勝手に遊ぶ。遊具も道具もない空き地の利用は、きっとこうして始まる。梅津雅史教諭も「放課後Dには空地のイメージもあったんですよ」とおっしゃった。部活動では絶対にありえない光景に、妙に生徒たちによる放課後活用の可能性を感じてしまった。
技術室では技術D。木工メインの活動だが、この日は担当教師が不在のためノコギリなどは使わない。ちゃんと自主管理できている。
教室では、けん玉の練習をするけん玉Dの生徒。立ちあげたものの、ほかに参加者がいなかった。それでも単独で活動を続けている。隣では筋トレDがタブレットを見ながら筋トレに励む。もう一人、一緒に活動していたが、自分のメニューを済ませて、この日はすでに下校していた。こんな自由もある。
別室では、生徒会役員のリーダー研修が行われていた。委員会の一つが「活動応援委員会」。前身は「応援団指導部」で、かつては中体連などに出場する生徒たちを応援する激励会を担当していたが、部活動がなくなり、活動の場を失っていた。
そこで、臨時生徒総会を開催して生徒会組織を改変、「応援団指導部」は学校全体を活気づけ、学校生活を豊かにする「活動応援委員会」として、24年度から放課後Dの運営をメインとして活動を再開した。教師主導で始まった放課後Dは、生徒が望んで生徒会が運営していくことになった。この日のリーダー研修では「どうすれば放課後Dに参加する生徒が増えるか」を話し合っていた。
委員長(2年生男子)は、入学したときはすでに部活動はなかった。「あ、そうなんだなっていう感じでしたね」と言う。「部活がないならないで」と気持ちを切り替えて、生徒会とともに技術Dでも活動している。「技術Dも楽しくやっています。『やりたい』と言えば、本当に自分たちがやりたい活動ができるので、そこをアピールすれば、もっと盛り上がるのではないかと思います」
これも芽吹きの一例。部活動のない中学校生活を過ごした彼らは、どう育って卒業していくのだろう。
「学校が目指している姿を生徒たちが語れるというか、放課後Dにかぎらず体育祭や演劇発表会や合唱発表会など、そのつど『この活動はなんのためにやるのか』と生徒たちに問い続けてきて、その成果が表れていると思います」(梅津教諭)
「今まで“当然だったこと”を、生徒たちが問い直しをかけて学校を変えていっているのが、今年度の生徒たちの姿です。2年生は『自分たちで学校をつくっていける』という言葉を使うようになりました」(堀教諭)
「自由」の扱いに慣れれば、部活動のイメージにとらわれず、生徒たちはもっと興味深いものを生み出せることだろう。
◆ 地域展開しても“教育の一環”
白新Uにはバスケットボールが4チーム、サッカー、ソフトテニス、軟式野球が各1チーム。文化部は、現状では放課後Dを自分たちで立ちあげることになる。
この日は、バスケクラブの一つ「SBCC」が練習を始めたところだった。精かんそうなそろいの練習着を身につけ、かなりの人数がいる。部活動風景と変わらない。大半は他校生だが、白新中生も参加している。大半の他校生が通っている中学校には既存の部活動があるが、あえて白新Uを選んだ。地域展開により、中学生にはそういう選択肢ができた。
白新U視察後は、こんなことが話題になった。「SBCC」をメインで運営するのは近隣校の現職教師。活動の日はほぼ定時に退勤して指導に駆けつける(17時30分~。それまでは別の指導者がトレーニングを担当)。勤務校で自分の業務をきちんと管理すれば、こういう働き方も可能。全国的な地域展開の場合でも、外部指導者の質・量が十分に確保できる保障はないので、教師の兼職兼業の形態はあてにされているはずだ。
実は梅津教諭も、お住まいの地域にあるサッカークラブの指導にかかわっておられる(メインで運営しているわけではない)。
高田教授が「勤務校ではなくても、部活動顧問としてもっていた意識とか熱量とか、学校教育活動の一環だという意識レベルは同じでいられるものなのですか?」と質問された。
梅津教諭はこんなふうに答えた。
「私はずっと部活動の顧問としてやってきたので、学校生活や部活動のさまざまな場面で教員が顧問であることのよさを感じています。そういう立場だった人間が地域のクラブで指導するとき、まずは、ここにいる子どもたちの人間的な成長を一番大事にしなければいけないと考えます。その上で、専門的なサッカーの指導を提供したいというモチベーションもあります。顧問として生徒をみる環境とは違うので、まったく同じかといわれると多少は違うと思いますが、根本のところは揺るいではいないと思います」
「SBCC」の“指導者”も、ときには体育館のステージ上で“部員たち”に勉強をさせることがあるそうだ。まさに教師の目線。あきらめずに頑張る姿勢やチームワークはクラブチームでも育つ。堀教諭は「総合的に部活動指導に長けている教員は本当にひと握りなんですよ」とおっしゃるが、それでも保護者は“クラブの指導者が学校の先生”であることに安心するし、高田教授も教師への信頼はあつい。それゆえ、〝学校における部活動〟を大事にしたいと話された。外部指導者についてはこんな注文をつける。
「学校の教育活動の一環として部活動が行われてきたわけですから、部活動を通してどのような人間を育成するかという理念においては、それを誰が担おうとも、変わるべきではないと思います。担い手が教師から専門の指導者になったのだから、これは教育の一環ではなく技術指導です、あるいは放課後の受け皿ですというのは、違うと思いますね」
教師は13~15歳の生徒たちを育てる専門家。その人たちが部活動を担ってきた。地域展開を優先して、部活動が学校教育に果たしてきた意義を軽視してはならない。
学校が安心して中学生の育成を委ねられる地域の環境整備を、各スポーツ連盟や芸術協会も積極的に協力して社会全体の責任として進めてもらわなければ困る。そうでないと長く部活動を担ってきた教師たちの“納得”は得られない。
◆ 新たな学校づくりの機会
最後に高田教授から、「部活動改革への現場からの回答の一例」としての白新中の取組の“講評”をいただいた。
「この取組は、“はまる形”の一つだと思います。新たな生徒会活動を含めて放課後Dのあの時間は、生徒の放課後の活動の事例になると思います。先生方にとっても、ご自身の時間の充実につながり、心のゆとり、時間のゆとりが新たな教育活動の創造にもつながっていくのだろうと思います。部活動の指導を続けたいという先生方の働き方をどうつくっていくのかと思っていたのですが、白新Uの先生や梅津先生のような形であれば続けられる。それもいいなと思いました」
中学校に部活動があるのが当たり前だった。でも一番の当事者である生徒は「ないならないで」と割りきった。教師も、部活動がない生活を思い描いてみたい。意外にウェルビーイングかもしれない。
「発展的解消という言葉があります。部活動を手放すことで何かがよくなれば改善。単に『できなくなるけど仕方ないね』では後退。何かを切って、何も得なければマイナスでしかありません。代わりに何かを伸ばすということを丁寧にやっていかなければならないと感じました」
堀教諭は「今のやり方は、白新中の最適解としてやっていますが、数年後もそうであるのかはわかりません。理念の共有とか新たな課題に直面したら、また最適解を求めなければならないし、それが学校づくりにもなると思います」とおっしゃった。
教師たる者、「中学生の成長には何が大事なのか」を問い直す歴史的な創造の機会だと捉え、自校の最適解、自分の納得解を見つけたい。部活動が唯一の解ではないはずだ。
【了】
次回の予定
9月1日(月)
授業参観~p4cによる道徳科~

