学研『教育ジャーナル』は、全国の学校・先生方にお届けしている情報誌(無料)です。
Web版は、毎月2回本誌から記事をピックアップして公開しています。本誌には、更に多様な記事を掲載しています。
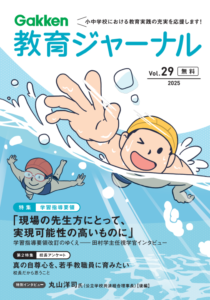
教育ジャーナル Vol.29-1
■授業参観~p4cによる道徳科~
自分の発言をみんなが聞いてくれる。こんな安心感が教室を包む
「誰にも言わないでほしいんですけど。ほんとに4年2組だけね」仙台市立田子小学校4年2組
【全2回】(第1回)
■授業参観
「誰にも言わないでほしいんですけど。ほんとに4年2組だけね」
仙台市立田子小学校4年2組 ~p4cによる道徳科~
自分の発言をみんなが聞いてくれる。こんな安心感が教室を包む。
全2回【第1回】
教育ジャーナリスト 渡辺 研
◆ 良好な学級風土の醸成
目新しい視点ではないのだが、この頃「学級風土」が気になりだした。
対話的な学びや協働的な学びが教室で展開されるようになったが、そういう学びが成り立つベースになるのが、良好な学級風土だとう。よそよそしい、ギスギスした空気の教室では、自分の考えや思いを安心して発言できない。前号の盛岡市立杜陵小学校6年生のかなり突っ込んだペア対話も、それを可能にする学級風土があるからこそだと思った。
対話を重ねることで良好な学級風土が培われ、良好な学級風土の中で対話的な学びや協働的な学びが深まるという相互作用はあるのだが、最初から好循環が生まれるわけはない。p4c(*1)がその循環のきっかけになるのではないか……そういう視点から仙台市立田子小学校(及川悦彰校長*2)4年2組の道徳の授業をお伝えする(昨年12月の授業)。
授業者の永井あやか教諭は、前任校が仙台市におけるp4cの最初の実践校のうちの1校で、そこでp4cに出合い、主に道徳の授業に取り入れてこられた。学級風土づくりにもいい影響があるとおっしゃる。
p4cの詳細は省略して、実施上の大事なポイントを挙げておく。
●円になって座る。お互いの顔が見え、全体の様子を見渡せ、場の空気を感じ取る。
●毛糸のコミュニティ・ボール(CBと略。柔らかいぬいぐるみ等でも代用可能)。挙手してCBを受け取って初めて発言できる(教師も含めて)という重要アイテム。
●約束(ルール)=①CBを持った人だけが話せる、②まだ話していない人を優先する、③話したくなければ(途中でも)パスできる、④傷つけることを言わない。CBを持った人の発言を静かに聞き、発言を邪魔するような不規則発言はしないのが絶対のルール。これを毎回必ず確認し合う。
●最後に対話の振り返り。
p4cの絶対の基本は「自分の考えを安心して言える(セーフティ)」という「セーフティの保障」だ。
このルールを守って子どもたちは話し合いを行う。4年2組の子どもたちはp4cが大好きで、授業参観後、集まってきた子どもたちから「今日、4年2組のp4cを見てどんなことを思いましたか?」と質問されたほどだ。道徳の授業だけでなく、金曜日は朝の会でも15分程度のミニp4c(身近なことがテーマで、子どもたちが話したいことを掲示板に貼っておく)を行っている。そこからどんな学級風土が醸成されるか、想像がつく。
*1 p4c。「ピーフォーシー」、「philosophy for children」のこと。これを「探究の対話(p4c)」と捉えて、東日本大震災・津波の2年後から、仙台市や白石市を中心に宮城県内の多くの小・中学校の教師たちによって実践されている。
*2 2025年度より加藤行宣校長
◆ 3つの候補からテーマを選ぶ
教室ではすでに机が後方・左右の壁際に寄せられ、子どもたちは丸くなって座っていた。ミニp4cでもテキパキとこのスタイルをとるそうで、すっかり手慣れたものだ。
まず教材文の音読。お話は、「正直な心」を描いた『ふくびき』(くすのきしげのり著)。
お母さんにバッグをプレゼントしたくて歳末大売り出し中の商店街にやってきた姉と弟。二人のお小遣いを合わせても買えなくてがっかりしたのだが、帰り道で拾った福引券で、なんと3等賞の赤いバッグを当ててしまった。大喜びする弟。でも、姉は一瞬ちゅうちょしたあと、「ごめんなさい。券は拾ったんです。これ、返します」といってバッグを返した。
このあと、物語はハートウォーミングな展開になるのだが、道徳の授業では「黙って持って帰って母にプレゼントしようか」それとも「正直に返すべきか」の葛藤に視点を置いてみんなで話し合う。
子どもたちは事前にこの文を読んでいて、そこから話し合う「問い」(テーマ)を自分なりに考えて提出していた。類似するものを永井教諭が3通りの「問い」に整理して読みあげる。子どもたちは顔を伏せたり、後ろを向いたりして挙手をする。ほかの人に左右されずに意思表示するための工夫だ。
子どもたちが選んだ「問い」は「ウソで当てたバッグを自分だったら返す?」。
3つの「問い」に大きな差はなかったのだが、不満のつぶやきなどはまったくない。それどころか、決まったとたんにノートに自分の考えを書き始めた。
「書けた? じゃあ、途中の人もペアでお話ししてください」
「自分だったら返す。理由は~」とすぐに教室中から話し声が聞こえてくる。こうすることで、まず自分の考えに確信をもつ。
考えの交流を終えたら、当番の子たちが真ん中に立って「約束」と「対話の道具=きっかけの言葉WRAITEC」(「本当にそうかな?」「なぜそう思うの?」など対話を促進する7つの言葉)の確認。ここまで永井教諭の指示もなく子どもたちがスムーズに進めてきた。クラスのまとまりが伝わってくる。
◆ その場面に自分を置いて
自分だったらどうするのか。もともとこの「問い」を考えた子どもたちの中の一人が、最初に発言する。「自分だったら返すと思います。理由は~」。内容を永井教諭が板書する。どんな考えが出てきたのか、子どもたちが確認できるようにするためだ。ほかの子と同じ意見でも、それが自分の考えなのだから子どもたちは気にかけずに発言する。
次々に手が挙がる。話し終えると、発言者が次の人を指名してCBをトス。こうして発言を回していく。教師も発言したいときは挙手してCBのトスを待つ。
「返したくないから持って帰る」「返さないと思う。言う勇気が出ない」「返します。返さないとママが『すみません、うちの子が』って返しに行きそうで」
現実の世界には〝正直な心〟だけでは決断できない事情もある。
「正直に言ったら、おじさんに怒られる」「正直に言ったら逆に褒められると思う」
物語のその後の展開(正直に言ったから、いいことがあったよ、という結末)は気に留めず、子どもたちはその場面の姉や弟に自分を置き換えて〝自分事〟として話す。
「返す」という理由の中にはこんな言葉も聞こえてきた。
「返さないとモヤモヤが残る」「後悔する」「罪悪感がある」
ずるいことをして券を得たわけではなく、福引のおじさんに損害を与えたわけでもない。それでも、返さないと言う子たちも、心の中に後ろめたさを感じていたようだ。
24人が「返す」「返さない」と話したあと、p4cは思わぬ展開になった。
【第2回に続く】
次回の予定
9月15日(月)
授業参観~p4cによる道徳科~②

