学研『教育ジャーナル』は、全国の学校・先生方にお届けしている情報誌(無料)です。
Web版は、毎月2回本誌から記事をピックアップして公開しています。本誌には、更に多様な記事を掲載しています。
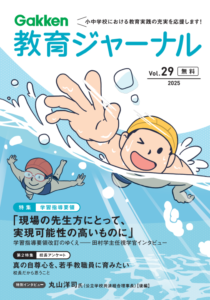
教育ジャーナル Vol.29-2
■授業参観~p4cによる道徳科~
自分の発言をみんなが聞いてくれる。こんな安心感が教室を包む
「誰にも言わないでほしいんですけど。ほんとに4年2組だけね」仙台市立田子小学校4年2組
今回は、p4cの展開と学級経営への影響についてご紹介する。
【全2回】(第2回)
■授業参観
「誰にも言わないでほしいんですけど。ほんとに4年2組だけね」
仙台市立田子小学校4年2組 ~p4cによる道徳科~
自分の発言をみんなが聞いてくれる。こんな安心感が教室を包む。
今回は、p4cの展開と学級経営への影響についてご紹介する。
全2回【第2回】
教育ジャーナリスト 渡辺 研
◆ つい、話したくなる空気感
永井教諭が挙手してCBを受け取った。子どもたちの話が出つくし、新たな視点を提示するときにもルールは守られる。話が熱を帯びているときは、教師が挙手してもなかなか指名されないこともある。
「どちらかというと、正直に言ったほうがいいという人が多い感じはするんですけど、『これは正直に言いたくない』と思ったことはありますか? なんでも言いますか?」
一瞬、子どもたちがザワついた。
「何もない?」
一人の子が意を決したように手を挙げた。
本当にちゃんと話ができる。
「お留守番のとき、〇×にお茶をこぼした。お母さんに『どうしたの?』と聞かれて『知らない』と言ったけど、すぐバレました」
軽い笑い声が起きる。
「学校のおたよりを出さなくて怒られたことが2回ある。『今日はないの?』と聞かれて『ないよ』とウソをついた」
告白した本人でさえ笑ってしまう和やかな空気の中で、いつの間にか〝告白タイム〟が始まった。
「2年生のとき~」「幼稚園のとき~」……ずいぶん過去の出来事に「ええっ!」と驚きの声。忘れてしまいたいことにかぎって、いつまでも覚えている。大人も同様。
「誰にも言わないでほしいんですけど。あ、4年2組だけ、ほんとにこの中だけね」
近くに座る子が「閉めたら?」と言い、別の子が素早く席を立ち、教室のドアを閉めた。秘密を外に漏らさない。こんな気づかいができる子どもたち。何かもめごとが起きても、すぐに「ごめんね」が言えそうだ。
「2年ぐらい経ってるけど、いまだに言ってなくて」
2年間、心の中にあった重苦しさが、今日、少し軽くなったかもしれない。話す勇気を得て、帰ってから家の人に「聞いてほしいの。実はね」と話したのだろうか。
延べ12人の〝告白〟を聞いた。p4cは〝つい、言いたくなる〟〝誰かに聞いてほしくなる〟という空気感を醸し出す。何度参観しても、いつもそう感じる。
永井教諭がCBを持って「もう1回聞きますけど、ウソで当てたバッグはどうしますか?」と発言した。やはり「返します」「返しません」「どうすればいいか、悩む」と子どもたちの考えは、最後まで〝それぞれ〟だった。
何か決まりをつくるわけではないのだから、道徳の授業はむしろそれがいいのかもしれない。現実の世界には、黙っておいたほうがいいこともある。でも「返さない」と言う子も、友達の考えや告白を聞いて、「ウソをつくとモヤモヤするのか」と思えば、実際の場面で、そう間違った判断はしないだろう。
ノートに授業の振り返りを書き、最後に今日のp4cを振り返った。
永井教諭が「①お話をよく聞きましたか ②自分の考えが授業の前と比べて深まりましたか ③自分の考えをお隣の人やみんなに話すことができましたか ④今日のp4cはセーフティの環境でできましたか」と問い、子どもたちは挙手で答える。「できた」なら真上、「できなかった」なら水平。挙手の角度で表現する。
全員が真上に手を挙げているわけではないが、正直に自分の気持ちを表現しても、先生や友達からとがめられることはない。
◆ 教室が安心できる居場所になる
授業後、子どもたちから少し話が聞けた。前述の「~どう思いましたか?」の続き。
「p4cって、どうして楽しいの?」――「4年2組のみんなの意見が回ってて、それで、『こういうこと思っているのか』、『いや、こっちもあるな』みたいに、やりとりができるのが楽しいんだと思います」
「自分の考えを正直に話せる?」――「正直に話せる人が多い。あんまり手を挙げない子もいるんですけど、その子もたぶん正直に言いたいなと思っているんだと思う。私自身は正直に話しています」
「みんな、言いたいことや聞いてほしいことがあるんだね」と言うと、「私はそう」「はい、そうです」という返答の中に「人によって違う」という声も混じった。4年2組は、〝それぞれの人〟が仲よく過ごす集団だ。
永井教諭にもお話を伺った。
「ふだん、あんまりしゃべらない人もあの〝告白〟の中にいて、道徳のときだけ手を挙げるという人もいます」
セーフティの保障が、子どもたちを安心させてくれるのだろう。
こんなこともあった。3年生から別室登校が続いていた子が、4年生の1月から教室復帰した。別室登校のときから道徳には参加できて、発言もしていた。テーマから外れた発言をすることもあったが、それでも周りの子どもたちはうなずきながら発言を聞いていた。
永井教諭は「p4cの力だけでこうなったわけではありませんが、発言して認められた経験が、教室での居場所づくりや安心感につながっていたのかもしれません」とおっしゃる。本当にそうなんだろうと想像がつく。
◆ 本質の部分を理解し合っている
授業中のこの雰囲気は日常生活にも及んでいるそうだ。
28人の学級でも、学習面や生活面で得意な子もいれば苦手な子もいる。〝みんな同じ〟ではなく本当に〝人によって違う〟。多様性を認め合おうといっても、細部では異なる人間同士の集団生活は、10歳の子どもたちの間にトラブルを生んでもおかしくない。
「p4cのときだけでなく、それぞれの本質の部分を理解し合っているように思います。だから、何か苦手なことがある人でも、周りの受け止め方を感じて、落ち着いて過ごせるのではないかなと思います。違っていてもいい、みんな同じだとおもしろくないよねというのが、生活の中にも生きていますね。人間関係も固定化していなくて、グループ化のトラブルもありません。2組は男女同数なので、p4cのときは男女隣り合わせに座ります。最初の頃に『男女順番に座ってね』と言ったことを、ずっとやってくれているんです」
このクラスの中では、本当の自分でいられる。それは学校で過ごす時間をかなり快適にしてくれるはずだ。4年2組ではこの当時、ある遊びがはやっていた。といっても全員が全員というわけではなく、中には興味がなくて加わらない子もいる。でも、その子たちが仲間外れにされることはない。
4年2組の両隣の2クラスでも、学級担任が興味をもち、p4cを実践している。若手の教師だそうだが、きっと学級経営に役立っていることだろう。
「なんとなく、柔らかい雰囲気がつくられているという感じがありますね」
ある朝のミニp4cで、子どもたちは「法律って本当に正しいの?」というテーマで話し始めた。その中で「道路に飛び出した子どもと車がぶつかったら、子どものほうも悪いのに、大人が犯罪者になるのは理不尽」と言った子がいたそうだ。
「『よく大人の立場で考えられるなぁ』『理不尽なんて言葉を知ってるんだ』と、私はひたすら感心して聞いていました」
本当に子どもなりに言いたいことがあるようだ。道徳の授業でもないのに、朝からこんなことを話し合える子どもたちの姿を見られるのは、学級担任も楽しいことだろう。
それぞれ個性があって、みんな一緒ではないのに、仲がよくて、お互いを尊重し合いながら正解のないテーマを論じ合える。1コマの授業を参観しただけでも、とてもうれしくなった。この子どもたちが動かす未来は、こんなふうにしてつくっていきたい。
【了】
次回の予定
9月29日(月)
真の自尊心を、若手教職員に育みたい~校長アンケート~

